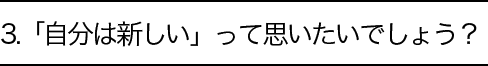5.年を重ねる度に自由になる
<プロフィール>
永井愛(ながい・あい)
劇作家・演出家。二兎社主宰。桐朋学園大学短期大学部演劇専攻科卒。「言葉」や「習慣」「ジェンダー」「家族」「町」など、身辺や意識下に潜む問題をすくい上げ、現実の生活に直結した、ライブ感覚あふれる劇作を続けている。日本の演劇界を代表する劇作家の一人として海外でも注目を集め、『時の物置』『萩家の三姉妹』『片づけたい女たち』『こんにちは、母さん』など多くの作品 が、 外国語に翻訳・リーディング上演されている。
――その後、二兎社は大石さんと永井さんの戯曲を交互に上演し、公演を重ねていきます。
二兎社を旗揚げして、わりとすぐに週刊誌からの取材が来たんです。『ぴあ』が出来たばかりの頃だったと思います。今みたいにホームページなんてないから、唯一の告知情報は『ぴあ』と新聞のイベント情報欄。その頃、ちょうど女性がリーダーの劇団が目立ち始めて“女の時代”って言われてたんですよ。
渡辺(わたなべ)えりさんの“3○○(さんじゅうまる)”とか、木野花(きの・はな)さんの“青い鳥”とか、如月小春(きさらぎ・こはる)さんの“NOISE(ノイズ)”とか。それで、女性がリーダーの劇団特集の後ろのほうに二兎社もちょこっと書かれたりしてね。
85年あたりには(動員数)1000人を超えていたんじゃないですか。だけど、1500くらいになってから、なかなか2000の壁を超えられなかった。静が辞める頃には、2000人超えてたのかな。
――テレビドラマの脚本に専念するということで、大石さんは91年に二兎社を退団されていますね。
そう、二兎社の旗揚げが81年だから、10年間一緒にやったんですね。ちょうど、私たちが40歳になる年でした。大打撃だったけれど、そこから逆に開けていくものがあったんです。30歳で劇作を始めた私が、劇作家として認知されるようになったのは、静が辞めた後の、40代の後半です。
――40代後半。
だからね、自分が劇作や演出で賞をもらうことがあるなんて、思ってもみなかった。それを言うと、「嘘でしょ」って言われるけれど、全くそういう対象になってはいなかったもの。いくらかは取材も来たり、劇評に取り上げてもらったり、ファンもいないわけではなかったけれど、自分はメインストリートではない脇の小道を一人で走っているような感じがあって。
私が演劇を始めた頃っていうのは、先ほどお話ししたようにアングラ第一世代の全盛期。次に、つかこうへいさんのブームがあり、そこに野田秀樹(のだ・ひでき)さん、鴻上尚史(こうかみ・しょうじ)さんが登場して脚光を浴びた。その全部が、二兎社のような日常的な芝居じゃないんですよね。だから、演劇っていうのは、時空を飛ぶような奔放なイメージが必要なのであって、日常的な言語でリビングを舞台に展開するような芝居は、テレビドラマと同じだっていう考え方が根強くあった。私たちのことを“お茶の間劇場”って言う人もいて。
でも、私たちが“二兎社”をつくったもう一つの理由は、「私たちは前衛じゃない」って認めたからなんですね。もう、無理して新しがるのはよして、身の丈に合った芝居をしようって。若い人って、「自分は新しい」って思いたいでしょう?
――ああ……!
今私のやっている芝居を知っている人はビックリするんですけど、私は大学の最後の2年間では“前衛劇ゼミ”にいたんですよ。前衛劇っていったら、いわゆる不条理演劇です。ベケットとかピンターとか、安部公房(あべ・こうぼう)だとか。そういう、いわゆるリアリズムでもなくウェルメイドでもない表現手法で、人間の実存そのものに迫ろうとする難解な芝居をテキストにしていました。
わけがわからないながら、新しい時代を描く方法はここにあると思ったし、ナンセンスな“笑い”には共感できた。でも、やりながら背伸びしているような、内面とは違うことをやっているような気がしてきて、自分が生きているのとおんなじ言葉で演劇表現を出来ないかなという思いはずっとあったんです。
静と出会った集団では、チェーホフも上演したりしました。でも、チェーホフはリアリズムといっても翻訳劇じゃないですか。長いスカートをはいて「ユーリャさん、恋をしたことはおあり?」なんて言うわけです。それを自然に言おうとして、一生懸命稽古しても、自然に言えるわけないですよね。「好きな人いるの?」「付き合ったことある?」っていう、女同士の親密な会話にはどうしてもならない。自分と同じ年代の役を演じているにも関わらず、なんか違わないかって、静とよく話しました。
当時、“等身大”っていう言葉が流行っていたんですよ。たしか、テレビディレクターの堀川とんこうさんが流行らせたんじゃなかったかな? テレビドラマの売り文句として出て来た言葉なんでしょうけれど、すごく新鮮に響きましたね。
それからは、“等身大”っていうものの価値がある種認められたというか、時空を飛ばず、誇張もせず、あえて等身大に描くということに、戦略的な意義が認められるようになった。
静がね、二兎社の旗揚げ公演の時にプレスシートをつくったんですよ。私は、そういうものの存在すら知らなかったんですけど、メディアや演劇関係者に向けて、企画意図や公演の内容を書いたものね。そこに、“二兎社はわかりやすく、希望のある芝居を目指す”って書いてあるの。で、「はあー」って納得した。
今思うと、あまりにもベタでちょっと引いてしまうところもあるんですけど(笑)。でも、わかりにくくて希望のない作品が“芸術的”だと尊敬されていた時代に、わかりやすく希望のある作品をやるっていうのは、ある意味挑戦でもあった。わかりやすすぎちゃって、とても挑戦者には見えなかったでしょうけど。
私がさんざん自分を褒めて、夜明けの風呂場で盛り上がった第一作は、「女の書いたものだから甘い」と、あっさり先輩に批判されました。「女の書いたもの」ってところにカチンときましたけど。父も、こっそり祖母に「甘い」と言ったそうです。
それでも私は、日常的な言語で“等身大”の芝居をやっていくことに意義を感じていました。20代は突っ張って、わからないまま前衛劇をやったりしたけれど、30代になって、正直になろうとした。“自分たちが何者であるか”ということを、かっこつけないで表現していこうと思ったんですね。そのことと、自分たちで劇団をやるっていうことはイコールだったんだと思います。

『許せない女』(1991年)。左から大石さん、永井さん
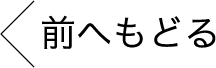
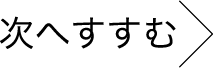
<公演情報>
『片づけたい女たち』(グループる・ばる)
作・演出:永井愛
出演:松金よね子、岡本麗、田岡美也子
日時:2014年3月8日(土)14:00開演
場所:ゆめぱれす(埼玉県朝霞市民会館)
備考:地方公演あり。詳細はグループる・ばる オフィシャルHPにて
グループる・ばる オフィシャルHP
********************
『鷗外の怪談』(二兎社)
作・演出:永井愛
日時:2014年秋公演予定
備考:詳細は二兎社オフィシャルHPにて
二兎社オフィシャルHP
>「特集記事」TOPに戻る