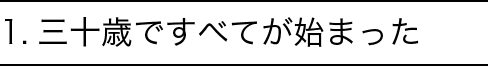5.年を重ねる度に自由になる
<プロフィール>
永井愛(ながい・あい)
劇作家・演出家。二兎社主宰。桐朋学園大学短期大学部演劇専攻科卒。「言葉」や「習慣」「ジェンダー」「家族」「町」など、身辺や意識下に潜む問題をすくい上げ、現実の生活に直結した、ライブ感覚あふれる劇作を続けている。日本の演劇界を代表する劇作家の一人として海外でも注目を集め、『時の物置』『萩家の三姉妹』『片づけたい女たち』『こんにちは、母さん』など多くの作品 が、 外国語に翻訳・リーディング上演されている。
――永井さんが30歳になったのは、テレビドラマ『セカンドバージン』などの脚本家として知られる大石静(おおいし・しずか)さんと、劇団“二兎社(にとしゃ)”を立ち上げた年なんですよね。1981年のことです。
そうですね、まさに今の石川さんみたいな年齢で。30歳になるっていう年に同じ卯年の大石静と。
――まずは、20代の頃のお話からお伺いできればと思います。
私、役者をやろうと思っていたんですよ。新劇女優。新劇っていうのは、言ってみれば商業演劇に対しての一つの文化運動であり、政治運動的な意味合いもあったんですね。社会改革運動の一つでもあるような。世の中はこのままでいいのか、というところから弱者の立場に立って社会問題を描いたり、戦争と平和についての芝居を上演したりするのが、多くの新劇の中心的なテーマでした。
私は“俳優座”に入りたくて、1970年に桐朋(とうほう)学園大学の演劇科に入ったんですね。当時は、そこに入らないと俳優座の受験資格がなかったんです。その4年間というのは激動の時代でした。世界的に学生の反戦運動が起きて、日本でも多くの大学で学園紛争があったんです。でも、既成左翼に与(くみ)せずに世の中を変えようとしていたはずの若者たちが、内部抗争というか、殺人までやってしまうようになった。“連合赤軍事件”が象徴的ですけれど、あれで一気に改革ムードが勢いを失って、またすごく保守的な時代になった。
そこからバブル文化に向かっていくわけですが、若者の文化的、政治的な闘争が盛り上がってから、終焉を迎えるまでの間が、ちょうど私の学生時代だったんです。私は学生運動には参加していなかったけれど、同じ若者として、気分的には左右されて、価値観を揺さぶられる。そうすると、新劇っていうものが、ちょっと色あせて見えてきたんです。
それまでは新劇の世界に入るのが、自分にとって一番いいことだと信じていたんだけれど、表現としておもしろいかどうかということを考え始めた。当時はアングラ演劇というのが出てきたんですね。わかります?
――はい。
“紅(あか)テント”の唐十郎(から・じゅうろう)さん、“黒テント”の佐藤信(さとう・まこと)さん、“自由劇場”の吉田日出子(よしだ・ひでこ)さん、串田和美(くしだ・かずよし)さん。“早稲田小劇場”の鈴木忠志(すずき・ただし)さんなど、私よりも上の世代の人たちが、そういう演劇の旗手でした。新劇を観ながら、アングラ演劇も観ていると、アングラのほうが新しい魅力にあふれているように感じるんですよね。そこに入りたいとまでは思わなかったけれど、そんな心の変遷(へんせん)があって、大学を出ても俳優座を受ける気がなくなっちゃって。
――卒業後は、どのような生活をしていたのでしょうか。
ある前衛劇団を受けたんですけど、落っこっちゃって。それで、言ってみれば就職浪人みたいなものですよ。新卒で採用されなかった場合、翌年はないっていうのが当時の常識で、既成の劇団に入る道はそこで閉ざされちゃったんです。
ただ、このまま家にいるのもどうかなっていうことで、家を出て、バイトに明け暮れて。そうしながら劇団を旗揚げしようって友人と相談していたんですけど、うまくいかなかった。25歳の時に、ある集団に拾われて、そこで、大石静に出会ったんです。でも、その集団はそれから2年くらいで解散しちゃって、行き場がなくなった。それで、私と静がパックになって、知り合いの劇団を渡り歩いて出させてもらっていたんですけど、それも「限界だね」となったのが30歳になるちょっと前でした。
――限界というのは。
このままお願いして、所属もしていない劇団に出させてもらっても発展性がないんじゃないかっていうのが一つです。あと、私は18歳で大学の演劇科に入って、静も別のところで養成所に入って、当時の時点で10年以上演劇に関わってきたわけですよね。他の仕事をしている人は一通りの仕事を覚えて、10年やれば若い人を指導するくらいの立場にはなっているわけじゃないですか。
でも、俳優は、もう掃いて捨てるほどいる。「どうしてもあなたに」なんてことは言われない。これはもう、自分が俳優をやっていきたいんだったら、「自分で場をセッティングするしかないね」と。それで、10年間演劇に関わってきたんだし、とにかく台本を書いてみようってことになったんです。で、それぞれがいい役でやりましょう、と(笑)。そう決めたのが29歳の時。これが“二兎社”旗揚げの経緯です。
締め切りの日を決めて、それぞれが一本書き、持ち寄ろうということになりました。約束の日、私は半分も書けていなかったけれど、静はちゃんと仕上げてきたんですよ。それが二兎社の旗揚げ公演になった『兎(うさぎ)たちのバラード』という作品です。30歳になる年に旗揚げしたわけだけれど、静の誕生日は9月で、上演は8月だったから、静は20代のうちに台本を書いたって言えますね(笑)。
私も20代のうちに書き上げたと言いたくて、旗揚げ公演が終わってから、また台本執筆に励みました。でも、明日が30歳の誕生日という日の深夜になっても、まだ仕上がらない。時計に目をやると、もう11時を回っている。その針が“12”の向こう側に行ってしまえば、私は30になっちゃうわけですよ。どうしても「20代で書いた」って言いたかったのに!
――(笑)。
30になる直前って、20代への妙な執着があるでしょ。それで、もしここで一本書き上げられなかったら、劇作家としては何もしない20代だったことになってしまうと、最後の数分までジタバタしましたが、とうとう時計の針が“12”の向こう側に行ってしまった。「あ、30……。うん、じゃあ『30歳にして初めて書いた』でいいか」って、すぐさま諦めの気持ちになりましたけど(笑)。その作品、『アフリカの叔父さん』は旗揚げの翌年、30歳のうちに上演されました。
20代の間は、人が書いた作品を人に演出してもらって、劇団のリーダーに頼って演劇活動をやっていくのが当たり前という意識でした。でも、二兎社で初めて、自分たちで作品を書き、劇団を主宰した。当時の自分がことさら“30歳”を意識していたとは思えないけれど、20代の自分のあり方から、はっきり一歩踏み出したわけですね。人に頼らずにやっていこう、と。
でも、それは実力をつけたからという理由ではなくて、だれからも必要とされていないっていう、決定的な認識があったからなんです。20代の時に所属していた劇団が解散して、そのまま辞めていても「辞めたんだ、へぇ~」とか言われるだけ。「それは残念だ」なんて決して言われない。だから、自分でやらないと何も始まらないということを形で示したのが、30歳になる年で、そこからすべてが始まったんですね。私の人生は極論すれば30から始まったって言ってもいいくらい。それまでは、その準備期間だったなと思う。

『兎たちのバラード』(1981年)での、大石静さん(写真中央奥)と永井愛(右端)さん
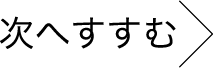
<公演情報>
『片づけたい女たち』(グループる・ばる)
作・演出:永井愛
出演:松金よね子、岡本麗、田岡美也子
日時:2014年3月8日(土)14:00開演
場所:ゆめぱれす(埼玉県朝霞市民会館)
備考:地方公演あり。詳細はグループる・ばる オフィシャルHPにて
グループる・ばる オフィシャルHP
********************
『鷗外の怪談』(二兎社)
作・演出:永井愛
日時:2014年秋公演予定
備考:詳細は二兎社オフィシャルHPにて
二兎社オフィシャルHP
>「特集記事」TOPに戻る