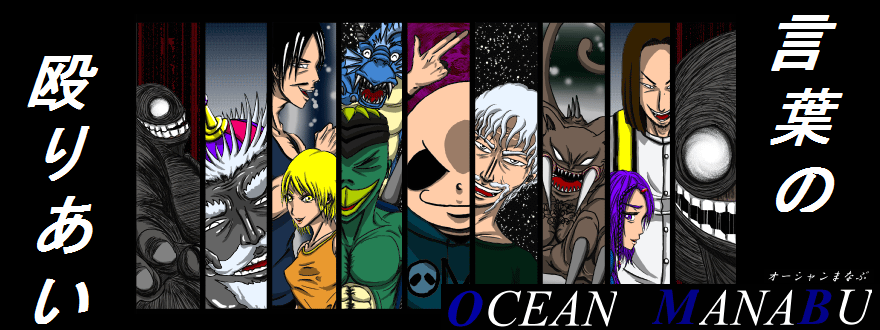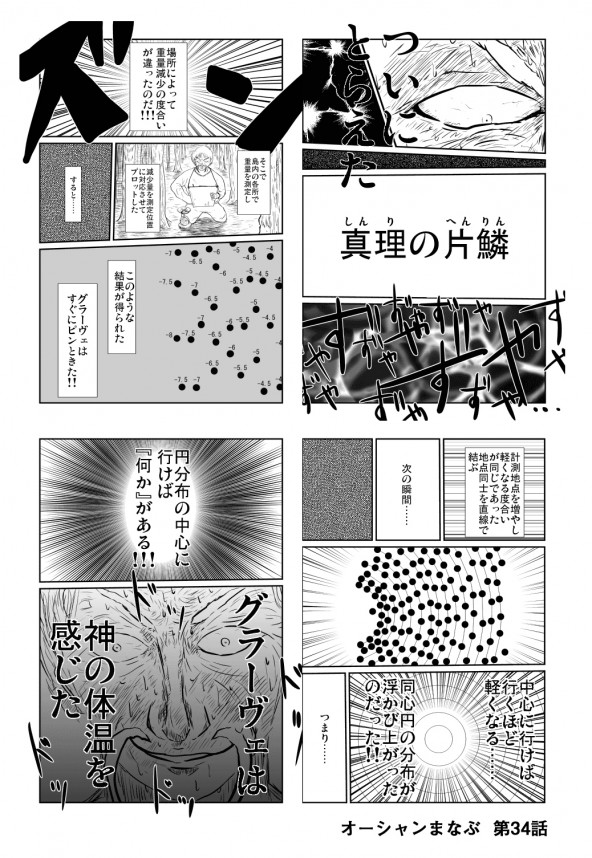『オーシャンまなぶ』誕生秘話
――拓須さんがWEB漫画を描き始めた経緯を教えてください。
2005年からです。今大学院の2年生なんですが、高校3年生の時ですね。漫画自体は小学生の頃からノートに描いていましたし、「漫画家になりたいな~」という思いもありましたけど、それは子どもが「パイロットになりたい」と憧れるのと同じレベルのものでした。僕の場合は、高校生当時に流行っていた「ブログランキング」というものに参加していて、その順位を上げるためのコンテンツとしてWEB漫画を描き始めたんです。一時期は小説やイラストなど、ジャンルにとらわれずにいろいろな創作をしていました。『オーシャンまなぶ』を描いたのは2006年からです。
――「伝説のきりかぶ」というブログですね。
ああ、そうです。懐かしい(笑)。次第に『オーシャンまなぶ』の反響が大きくなっていって、ブログからWEB漫画の更新が中心になったんです。そして、『オーシャンまなぶ』を描き始めて1年ほど経った頃に「ニュー速クオリティ」という、2ちゃんねるのスレッドを編集した「まとめブログ」で紹介していただいたことで一気に読者が増えました。読者の方の感想やコメントを糧にWEB漫画を描いてきたので、「こんなに見てくれている人がいるんだ」と実感してからは、遊ぶ時間を削るレベルで漫画を描くようになりました。
――その後は、1日あたり1万前後のアクセス数を安定して記録していますね。現在は商業誌の制作を優先して更新が止まっていますが、更新時は2万近いアクセス数がありました。読者が増えるにつれて、「幼少時代の憧れと同レベル」だった漫画家への思いも熱を帯びてきたのではないでしょうか。
そうですね。最初は現実的な選択肢には入っていなかったんですけど、出版社の方からのアプローチをちょくちょく受けるようになって「もしかして、漫画家になれるんじゃ……」という希望が出てきました。
――『オーシャンまなぶ』を描き始めたのが大学生当時。現在、拓須さんは大学院に通っていますが、進路を選ぶにあたって、どのような選択をしたのでしょうか。
多くの学生は、大学3・4年生で就職活動をしますよね。でも、僕がそこで就職活動をせずに大学院への進学を選んだのは「学生生活という“猶予期間”を伸ばすことで、何か起こせるんじゃないか」という希望を抱いていたからなんです。
――そして、インタビュー冒頭で話してくださった通り、編集者からのコンタクトがあったわけですね。しかし、商業誌での連載準備を進める一方で、拓須さんは今春から社会人として働くことが決まっています。何かしらの葛藤があってのことだと思いますが……。
実は、大学院1年生の時に漫画家になるのを諦めたんです。「これがラストチャンスだ」と思って出版社に持ち込むための漫画を描いたんですが、読み切り作品を描くのが初めてだったこともあり全然うまくいかなくて。清書もあまりに大変で「漫画を仕事にするのは無理だ」と、結局持ち込みはせずに就職活動を始めました。正直、WEB漫画である程度の自己実現を果たせていたので、「就職してからもWEBで描き続ければいい」と思っていたんです。でも、就職先が決まった後に漫画原作の話をいただいたて。
やっぱり、今までアプローチできなかった層にも自分の漫画を読んでもらえるというのは、WEB漫画にはない魅力なんです。決して容易ではないと思いますが、春からは漫画と仕事を両立していくことを決めました。
WEB漫画の未来を拓く
――WEB漫画と商業誌との大きな違いに「担当編集者の有無」があります。その違いをどのように感じていますか?
編集者の方は、さまざまな内容や情報の取捨選択によって、作品を方向付けていく力が本当にすごいです。WEB漫画の作品は編集者がいない分、作者の個性の塊のようなものが作品に表れますが、作風が濃すぎて一般受けしづらいというか。そこがWEB漫画の魅力である反面、一般層への広まりを邪魔する障害にもなっていると思います。この先、WEB漫画を一般の人に広く見てもらうには、『ONE PIECE』クラスの作品がWEBで連載するぐらいのインパクトが必要だと考えています。WEB漫画出身の作家が商業誌で人気になって、WEBに戻るというのもアリです。
――WEB漫画出身の拓須さんや『ワンパンマン』作者であるONEさんの今後の活躍に注目している人も多いと思います。
WEB漫画からデビューした「第1世代」が『ヘタリア』や『Working!!』の方たちなら、ONEさんや僕たちは「第2世代」。僕らが商業誌で成功するかどうかは、出版業界におけるWEB漫画全体の評価にしばらく影響すると思っています。「WEBで今話題の作家を連れてきました」といって失敗すれば、「WEB漫画って大したことないじゃん」と見限られますし、成功すれば「WEB漫画ってすごいんだな」と注目されるはずです。出版業界に革命が起き、読者と作者の両方がもっと幸せになる――そのキッカケになりたいと思っています。